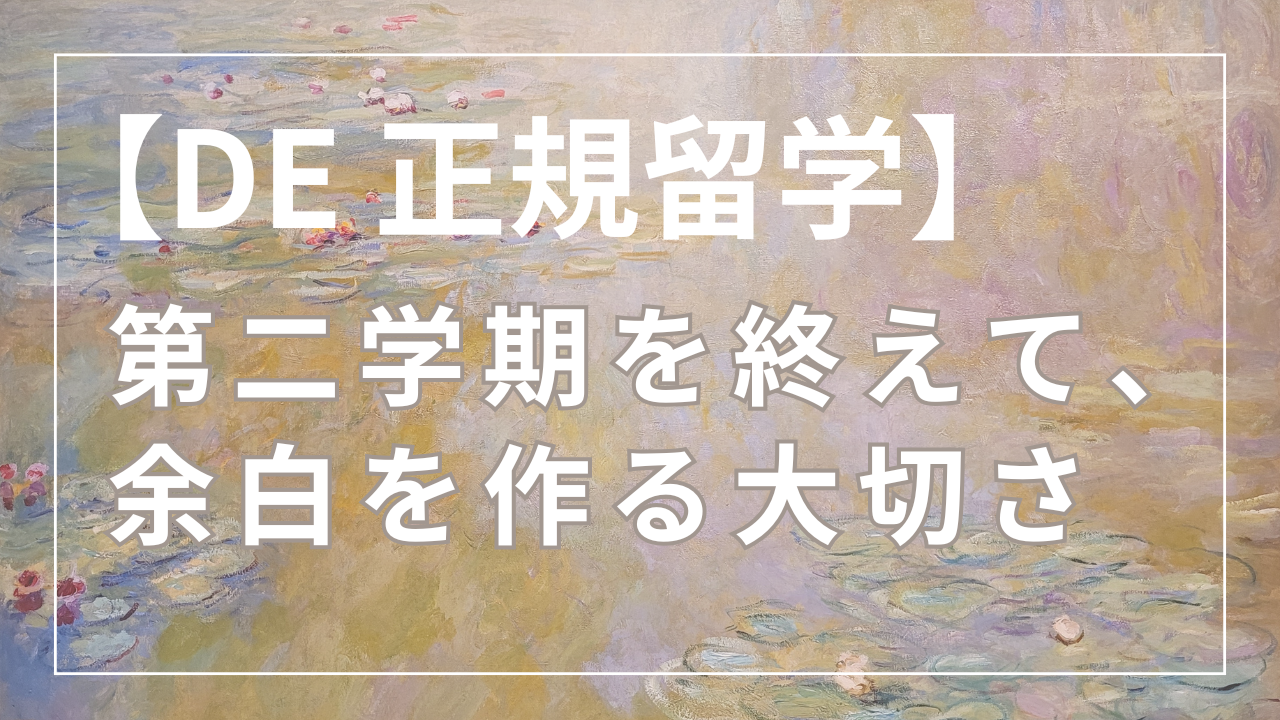第二学期を終えて感じたことは余白を作る大切さです。
実際に第一学期目とどう違ったのか、失敗と第二学期目の成果について話したいと思います。
Contents
第一学期目の振り返り

第一学期目の失敗
第一学期は、思うようにいきませんでした。
最大の理由は、多くの講義を欲張りすぎたということです。
片道1時間もかけて大学へ行くのに、
たった1つの講義のためだけでは効率が悪いと感じ、
ドイツ語の授業を多めに履修しました。
さらに言うならば、副専攻選びを失敗し悲惨な目に遭いました。
副専攻選びの失敗についてはこちらのブログ↓↓
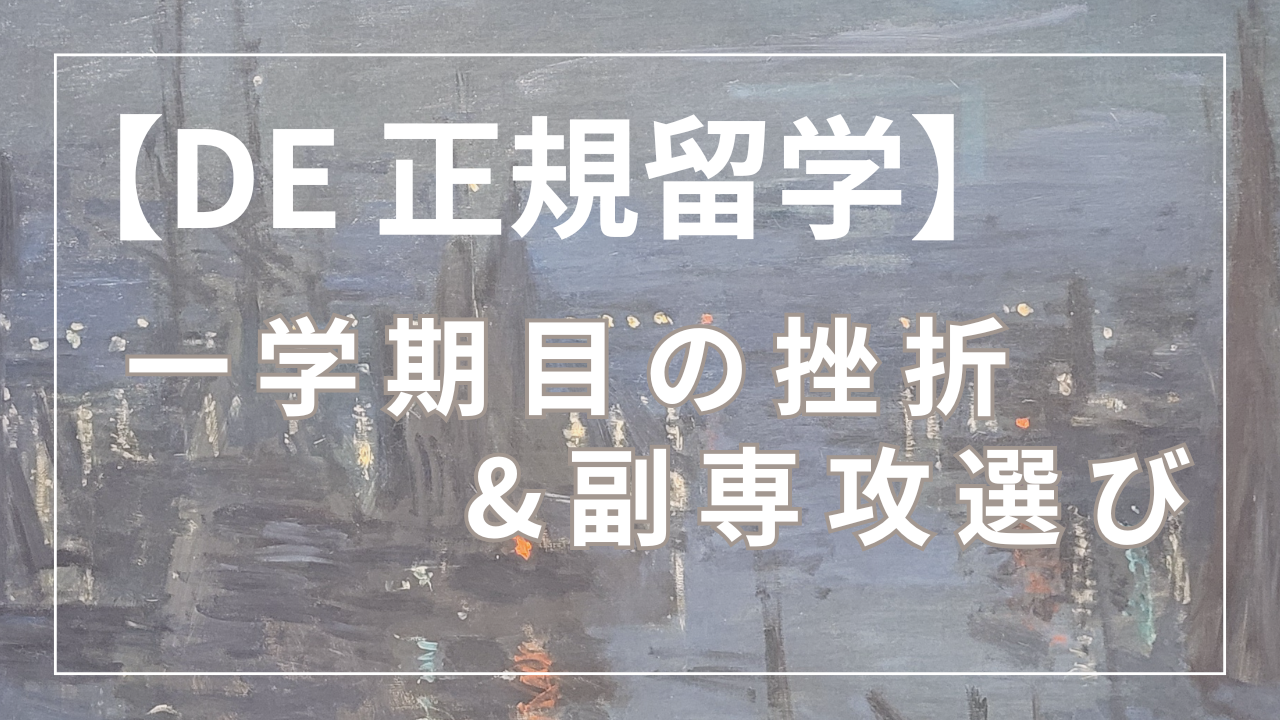
ドイツ語の授業に参加して良かったところ
もちろんこの選択には良い面もありました。
例えば、ドイツ語の授業を通じてイタリア人の友達ができ、
また美術史の先輩からもテストの方式など有益な情報を得ることができました。
さらに、中国人の学生が日本語のタンデムグループを作っていて、
その後偶然会った時に教えてもらえたりしました。
特に「人脈づくり」という点では、非常に有意義な学期だったと思います。
さらに講義におけるドイツ語の土台作りをすることができたのは良かったです。
毎日大学へ行った結果

一応、イタリア語が週に2回あって、美術史も3つありました。
(始めの1ヶ月は歴史学のプロセミナーと講義1つあった)
そのおかげで毎日大学へ行って講義を受けていました。
慣れない言語での学習ということもあり、想像以上に疲れるものでした。
確かに時間は以前よりはありましたが、
常に走り続けているような状態になってしまいました。
そんな日々でストレスが溜まってしまって、だらだらと復習していました。
そして試験では美術史のテストとレポート課題とイタリア語しかできました。
一応3つ合格したと言えば聞こえはいいですが、
美術史に関しては基礎編ということで、
誰もが受かるような簡単なテストでした。
そのため、もう一つの美術史の口頭試験も受ける予定でした。
ただ復習が間に合わない、ということで断念しました。
因みにドイツ語の授業は別に交換留学生でもなかったので、
私もそれ以外の正規留学生は基本的にテストは受けてません。
(受けることも可能ですが、特に学部では不要な単位なので。)
第二学期の工夫

メリハリのつける
休む時は休み、メリハリをつけて息抜きと勉強の両立が大切だと思いました。
この経験を踏まえ、第二学期目はスケジュールを見直しました。
つまり、計画的に『オフの日』ということです。
- 大学へ行くのは週2日のみ+1日はイタリア語のオンライン授業
- 木曜日は「友達に会う日」として設定
木曜日は、もともと自由参加の日本学のチュートリアルでしたが、
最初の方は行っていませんでした。
しかしタンデムパートナーと会い始めたので、
毎週木曜日は「友達と会う日」ということで、
自由参加の日本学のチュートリアル(ゆるい復習会)に参加することにしました。
(やはり1つだけのために大学へ行きたくはないので。)
そもそも、タンデムパートナーとの出会いも、
講義の後に友達とカフェへ行ったときに掲示板の貼り紙を見つけたのがきっかけでした。
さらに講義後にMittelbau(講師)とも話す機会ができ色んなことを毎週話し込んでいました。
またタンデムパートナーとは講義の内容をプレゼンすることで、
口頭試験の対策にもなったので、とても有意義でした。
つまりゆとりを持つことで、新しい出会いがあり、
そして『オフの日』にこそ、アウトプットができたということです。
第二学期目の工夫/成果
冬休みがあったことで、十分復習できたこと、
試験やレポート提出が分散されていたことが大きいですが、
その結果、
テスト3つ(イタリア語、日本学、美術史の口頭試験)
レポート課題2つも提出完了(一つはレポート課題の練習で簡単)
と、第一学期よりもはるかに良い成果を出すことができました。
もちろん今回は1学期の失敗や人脈があっての
今回の『実り』だった部分も確かにあります。
反論:早く卒業したい?
一番良かったのはゆとりを持つことでメリハリつけて学べたことです。
というと、早く卒業したいと言うような反論はあるかと思います。
勿論、各々色んな状況を抱えているので、
一括してそれを否定することはあえては言うことはできません。
留学ではネイティブよりも倍以上の時間が必要
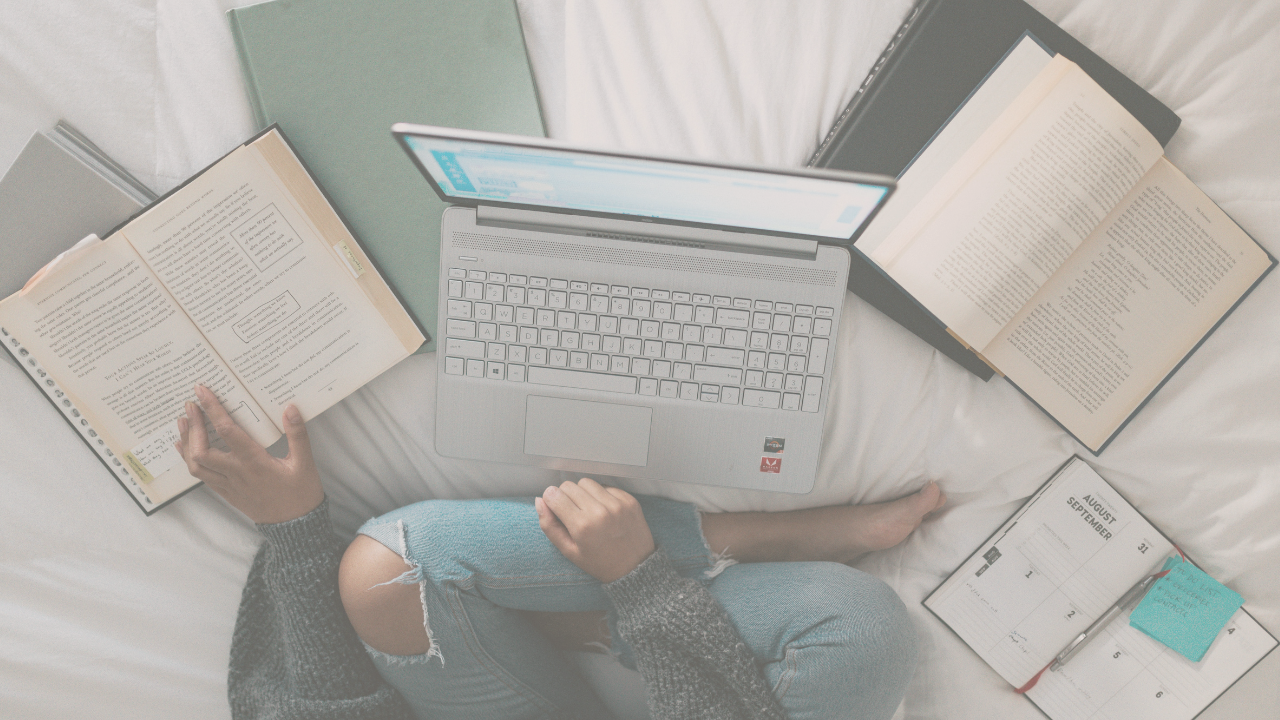 一つだけ確かなことを話すと、
一つだけ確かなことを話すと、
留学ではネイティブよりも倍以上の時間が何事にもかかります。
それが不慣れな外国語なら尚更です。
確かにそれはネイティブよりも多くの時間をかければいいだけの話です。
私もネイティブよりも多くの時間を復習に費やしたと思います。
しかしそうは言っても人間の精神力、体力は誰もが一緒くらいです。
1日に学習できる分量はネイティブと対して変わりません。
長期的に計画を立てるが、無理な計画は立てない
つまり物事は長期的に計画を立てるが、
無理な計画は立てないということです。
例えば、私は口頭試験があるのにむけて、
2ヶ月前から毎週タンデムパートナーにプレゼンしていました。
タンデムパートナーにプレゼンする前には勿論復習をするし、
それが本番のように活用していました。
しかし、明らかに多い講義、
8-10講義くらいを取得するのはそれは限界を超えていると思います。
そうしないと自分の望む期間で卒業できなければ、
それは無理な計画です。
仕方ないことを受け入れないといけません。
(勿論本人のドイツ語、英語力という能力の違いもありますし、
外国語にどれくらい依存するのかという分野にもよります。)
ゆとりを持つことは少しマイペースかもしれませんが、
大学へは何も『卒業』だけを求めているわけではないと思います。
学業以外にもクラブやイベントに参加したり、
友達との時間を大切にすることは後々の大学生活、
はたまた海外生活では重要なことだと思います。
まとめ
今後の方針
2セメスター目の経験を踏まえ、3セメスター目も同じような方針で進めようと思います。
「学ぶこと」と「余白を作ること」は両立できるし、
むしろバランスが取れていた方が効率よく成果を出せるという実感を得ました。
無理をせず、必要な時間を確保することが、
結局は学びの質を高めるということを学んだ今学期でした。